こんにちは。yoshiです。
これまで、一般NISAとつみたてNISAの比較やiDeCo単体では色々記事にしてきましたが、そういえば、結構大事なこの2つの比較記事は出してませんでしたね。
ということで、今回は『つみたてNISA』と『iDeCo』の内容を比較し、その結果どっちを優先して始めた方がいいのかを検討し、僕なりの結論を出してみようと思います。。
それでは、よろしくお願いいたします。
まず最初に両者の仕組みとメリットについて簡単に見ていきましょう。
運用可能額は一律年間40万円
積立投資の運用益が20年間(※)全て非課税になります。
(※積立を行った年から20年間で、現状2042年まで積立可能)
デメリットとしては元本割れのリスクと損した時に税制上の恩恵を受けられないこと(損益通算不可)と、最初の商品選びが意外と難しいといったところでしょうか?
商品が限定されすぎているといった意見も見聞きしますが、個人的にはもう少し優良インデッファンドや一定数のアクティブファンドに絞ってもいいような気はしています。
【もう少し詳しい解説はこちらの記事↓】
運用可能額は職業や企業年金制度の有無によって変わります。
年間144,000円~816,000円です。
こちらは2022年の改正で最高で65歳まで積立可能となります。(延長されるのは国民年金の加入者なので、労働者である必要がある)
iDeCoも積立投資の利益や定期預金の利息は非課税です。
また、年間掛金の全額が所得控除となる節税メリットもあります。
デメリットとしては、『資金拘束』『元本割れのリスクのある商品もある』『金融機関によっては手数料が高い』『手続きが煩雑』『対象者が限定的』などなど意外と上がってきます。
つみたてNISAよりも、制度や投資・金融についての知識がないと難しい制度のように思います。
【もう少し詳しい解説はこちらの記事↓】
また両者のメリットである『運用益に掛かる税金の非課税制度』は、あくまで運用で利益が出れば非課税にしてくれる権利を持つということであり、誰もがその恩恵に預かれるということを保証するものではありません。
もちろん優良インデックスファンドを長期運用すれば、過去実績から高確率で利益を得られるとは思いますが、投資に絶対はないということは念頭に置いておかなければいけません。
| つみたてNISA | iDeCo | |
| 対象 | 20歳以上(※※)の国内在住者 | 20歳以上~65歳未満(※※※海外居住者含) |
| 非課税期間 | 20年間(※) | 65歳まで(運用は5年延長可能) |
| 最大年間投資額 | 400,000円 | 144,000円~816,000円 |
| 非課税(総額) | 40万円×投資期間 (開始時期によって異なる) (2018年開始で最大累計1000万円) | 職業や時期により異なる 例)企業型DCのないサラリーマンが30年積立 27.6万円×30年=828万円 |
| 節税メリット | 運用益に掛かる税金が非課税 | 運用益に掛かる税金が非課税 年間掛金全額が所得控除 受取時の控除 |
| 投資対象 | 金融庁の認めた投資信託と一部ETF | 各証券会社で設定された投資信託や定期預金 |
| 投資方法 | 基本は定期定額積立 毎日・毎週・毎月なども可能 設定をいじることで一括投資も可能 最低100円からの少額投資 | 年間掛金の上限までを1年間で分割払い 年間一括も可能 月ごとに変更も可能になった 最低5,000円から |
| 資金出金時期 | いつでも可能 | 原則60歳まで出金不可能 |
| 売却 | いつでも可能 | スイッチング(投資商品の乗換) 出金は不可 |
※※2022年4月から18歳に変更
※※※2022年の改正後に年齢の延長と海外居住者も追加 第2号被保険者(サラリーマン)の下限の制限は記載がないので未成年でも対象者であれば可能
『どちらを優先していくか?』を考える前に1つお伝えしておきます。
資産運用を行う上で最も重要なのは『投資運用で資産を作る目的を明確にする』ことが重要であると考えます。
投資目的が老後資金であるのか、10年後までに資金を5倍にしたいなど様々な目的があると思います。
10年後に資金を作りたいのに、長期投資向けの商品だけでは達成が出来ない可能性は高いですし、逆に老後資金を作りたいのに投機的な手法を取っていては思ったより資産が増えないどころか資産を大きく減らしてしまうかもしれません。
資産運用の目的は人によって違いますし、取れるリスクや投資期間も人によって違います。
まずは自身のライフプランを含め、投資目的を明確にしておきましょう。
それではこれまでの情報からどちらを優先していく方が良さそうか検討していきます。
両者の特徴で最も異なるのは以下の2点だと考えます。
①資金拘束の有無
②所得控除(節税)の有無
これらで意見が分かれると思います。
共通メリットは運用益にかかる税金の非課税がありますが、これはあくまで結果に付帯するメリットです。
上記でも触れましたが、運用結果が元本割れとなれば非課税メリットはない訳です。
そう考えれば、iDeCoの節税メリットは確実に受けられるのは強いと思います。
これなら『iDeCo』優先で良さそうにも思えますが、ここでネックになるのが「資金拘束」です。
iDeCoは「年金」と名が付くだけあって、投資目的が老後資金の形成です。
その為、現在一般的な定年である60歳までは資金を拘束されるのは仕方ないですし、逆に強制的にしてくれていることで、投資初心者にありがちな下手に途中で解約してしまわないというメリットとも考えることも出来ます。
といっても、個人によってライフイベントが起こる時期は異なります。
特に若年層は収入や生活防衛費、所得の源泉も限られますし、結婚や出産・育児・教育、マイホーム購入や引っ越し、親の年齢によっては介護資金も必要になるかもしれません。
もちろん年齢だけでも区切れません。
結婚や出産、住宅ローンを組む年齢もどんどん年齢の幅が広がっています。
なのでどんな年齢層の方でも有事の際に、資産がiDeCoのみだと資金拘束は大きな重荷となります。
(iDeCoも一応解約は可能ですが、条件がかなり厳しいです)
そう考えるとやはり『つみたてNISA』の方が優先すべきか・・・
やはり『つみたてNISA』と『iDeCo』は一概にどっちを優先すべきという答えは出なさそうです。
ですが、記事にするかには僕なりの結論は出さないといけないと思いますので、次のブロックで結論をまとめさせて頂きます。
この記事を書くにあたり、色々な方の意見も見てみましたがどちらを優先していくかという点では両者とも意見の分かる部分もあり、なかなか難しいなと思いました。
そしてやはり『資金拘束』が一番のポイントになりますかね。
個人的には年齢層というよりも、『余裕資産の大きさによって優先すべき制度は変わる』と考えます。
将来の出費に関わる不確定要素も考慮した上で、積み立てた投資資金は現役時代に使うことは絶対にないと断言できるなら『iDeCo優先』でいいと思います。
出費に関わる不確定要素も多く、もしかしたら日々のキャッシュフローや生活防衛費だけでは不足するかもしれない。積立投資資金は引き出せる状態にしておきたいという人は『つみたてNISA』を優先させるのが良さそうです。
恐らく後者の考えの方の方が圧倒的多数だとは思いますので・・・
【結論】
つみたてNISA満額が優先、余裕資金が出たらiDeCoを開始する!
あくまで僕なりの結論ですので、他の方の意見も参考にしつつ、ご自身で最終判断を下してほしいと思います。
ここまで『どっちを優先?』という点に絞ってきましたが、一般NISAとつみたてNISAとは違ってこれらの制度は併用も可能です。
なので資金に余裕があれば、両方を積み立てていくのがいいと思います。
将来資産形成でのとりあえずの目標は、両方を満額を目指したいところです。
また、つみたてNISAとiDeCoでは選べるファンドや商品も異なるので、どういう組み合わせがいいのかも迷うとは思います。
例えば、つみたてNISAは基本的には株式のみのファンドなので、iDeCoは債券やREITなど他の資産クラスを組み合わせてみるなどですね。
個人的にはどちらも将来の資産のコアにすべき制度だと考えるので、両方とも優良株式インデックス100%でいいとは思っていますが、この辺は個々の考え方やリスク許容度にもよりますね。
あとは夫婦の場合ですかね。
これも夫婦のつみたてNISA満額を目指し、余裕資金に応じて順次iDeCoを取り入れていくでいいと思います。
専業主婦の場合は、節税メリットはありませんが、非課税メリットは大きいので個人的にはiDeCoも検討余地は高いと考えています。
もう一つは50代以降の方の場合ですが、こちらはiDeCoの制度上受け取れる年齢が後ろにずれ込みますので、iDeCoよりはつみたてNISA優先でいいと思います。
この方が本格的な老後(70歳以上)に備えが利きますしね。
いかがだったでしょうか?
「投資に正解はない」ことと同様に制度を選ぶにしても、正解というものはないと思います。
これは一人一人状況は違うし、将来のライフプランも異なるからです。
もう一度結論を書くと、
『つみたてNISA満額を優先し、余裕資金を作れるようになったらiDeCoも開始する』
ただ、将来の資産形成ばかり考えると、どうしても『今』使う力が衰えていくとも思います。
浪費はあまりしてはいけませんが、この辺りも上手くバランスを取りながら、若いうちにしておいた方がいい経験などには積極的にお金を使って欲しいとも思います。
ということで、長くなりましたが今回はこの辺で!
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

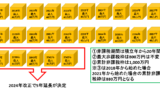







-120x68.jpg)
コメント