概要
①証券会社などでジュニアNISA専用口座を開設する。
※未成年総合口座も必要
②2023年で廃止が決定したが、それまでは年間80万円を投資可能
③2023年までは引き出し制限がある
④2024年以降は改正により引き出し自由になる
⑤ジュニアNISA廃止に伴い、2023年末時点で口座名義人(お子様)が対象年齢(※)の場合、継続管理勘定(非課税口座)へロールオーバーが出来、非課税運用が可能
(※追加投資は不可)
(※)2022年4月1日より成人年齢が18歳に引き下げられるのもポイント!
ジュニアNISAでの18歳の定義は、『3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで』
分かりにくい書き方ですが、『一般的に高校3年生の12月31日まで』と読み替えてOK


非課税の対象は、値上がり益と配当金です。
この金融庁のHPでは5年間非課税としかありませんが、継続管理勘定での18歳までの非課税運用は可能となります。
2016年からジュニアNISAを始めている方は、2021年からは非課税管理勘定へのロールオーバーの申請が必要です。
2023年末でジュニアNISA口座が廃止になったら、『継続管理勘定』へは自動的に移管されます。
注意点
①ジュニアNISAも1人1口座に限り開設できる。
②運用資金は、口座開設者本人(未成年者)に帰属する資金に限定
※登録親権者の口座からでも大丈夫な場合あり
③非課税枠は年間80万円まで(2023年12月31日まで)
④非課税枠は未使用分があっても、翌年以降へ繰越は不可
⑤18歳の定義=3月31日時点に18歳である年の前年の12月31日まで
※一般的に高校3年生の12月31日
⑥払い出しは18歳になるまで基本的に出来ない(災害等やむを得ない事情で例外有り)
※但し、2024年以降は引き出し制限もなくなる!
⑦値下がり等の損失と他口座での利益との損益通算は不可
⑧ジュニアNISA以外の口座で保有する金融商品の移管は不可(その逆も不可)
⑨国内上場株式の分配金は「株式数比例配分方式」で受け取れば非課税!
⑩投資信託の分配金の内、元本払戻金(特別分配金)は元々利益ではないので非課税(メリットなし)
というか、このようなタコ足分配型の商品には手を出さないで!
⑪2023年までに従来の非課税期間(5年間)が終了する人は『非課税管理勘定』へのロールオーバーの申請が必要
メリット・デメリット
【メリット】
①非課税で運用が可能
一番のメリットは、譲渡益(売却益)や配当金に掛かる、国内課税(20.135%)が非課税になる!
特定口座では、国内株式では10万円の利益が出ると20,315円の税金が掛かるのですが、ジュニアNISAであれば、10万円が丸々利益になります!
※海外ETFなどの場合、現地課税は掛かります。(米国で約10%)
②教育資金の準備に活用可能
0歳から始めれば、18年間の長期での運用が可能となります。
インデックス株式の投資信託での複利効果も十分に期待できる年数ですし、貯蓄などに比べて大きな利益が期待できるかと思います。
但し、インデックス型の投資信託と言えども、暴落リスクは当然ありますので、全額投資での運用はお勧め出来ません。
個人的には最低でも50%程度は定期積立貯蓄や学資保険などの安全資産での確保が必要かと考えます。
③金融リテラシーの教育になる
残念ながらお金や投資の教育はほとんど学校教育では行われません。
お子様名義の証券口座を持ち、金融商品について触れさせることは将来的に大きなメリットになると思います。
投資信託の仕組みについての勉強でもいいですが、教える親側もなかなか難しいということであれば、国内株式の株主優待などはお子様名義で優待商品が届いたりしますし、分かりやすいかなと思います!
実際、これらはジュニアNISAでなくても未成年口座でも行えるので、ジュニアNISAの枠で出来ない投資をしたい場合はこちらも検討の余地はあるかと思います。
【デメリット】
①元本割れリスク
投資信託や個別株式での運用がメインになるので、当然ですが元本割れのリスクもあります。
絶対に儲かる手法などありませんのでそこは理解して始めましょう!
②金融機関の変更は手間
一度申し込みをすると、移管の変更手続きをしないといけません。
選ぶ金融機関によって、投資信託などの商品も大きく違いますので、申し込み前によく検討する必要があります!
ここは、親御さんの勉強が必要ということですね!
③2023年12月で制度終了
これはデメリットだけとも言えません。
これまで18歳まで引き出し制限があったものが撤廃になるのはメリットだと思います!
また18歳になるまでは継続管理勘定で非課税運用もできるのはいいですね。
デメリットとしては、追加融資が出来ない点です。
よって2021年から始めた場合、21年~23年までの3年間で240万円の投資が可能です。
一括投資に近い形になり、時間分散効果が薄いというデメリットはあると思います。
ただ、一括投資と定額積み立てを比較して、一括投資の方が成績が良かったという時期もあるので一概にデメリットとも言えません。
この辺りは各家庭の考え方と運用予算次第かと思います。
ジュニアNISAの対象投資商品
①株式投資信託
②国内上場株式
③外国株式
④国内ETF
⑤海外ETF
⑥ETN(上場投資証券)
⑦国内REIT
⑧海外REIT
⑨新株予約券付社債(ワラント債)
となっています。
また、証券会社によって投資対象商品が異なるのも特徴です!

ジュニアNISAで外国株式を運用したい場合は、現状ではSBI証券一択ですね。
投資信託や国内株式であれば、楽天証券やマネックス証券でもいいかと思います。
出口
継続管理勘定が終了する年に何をしたらいいか?
基本的には3パターンに分けられると考えます。
①一般NISAへ移管し、
非課税運用を継続する
一部売却し現金化も可
②お子様名義のつみたてNISAを開設し、
継続管理勘定からは特定口座(又は一般口座)へ移管する。
全部もしくは一部売却も可
※特定口座へ移管する場合は、ここからの利益に対しては課税されます。
③この段階ではNISA口座は開設せずに
継続管理勘定から特定口座へ移管する
または教育費の為などに全部売却して現金化する
また、教育費に使いたい場合はこの前段階として、
最終局面での暴落リスクを回避するため、
必要額が確保できた時点で利確するのも一つの戦略だと思います。
まとめ
①ジュニアNISAは2023年12月31日で終了
②その後は引き出し制限がなくなる
③非課税期間はお子様が18歳になるまで(高校3年生の12月まで)
④メリット・デメリットは理解して行いたい
⑤ジュニアNISA対象商品は証券口座で異なるので事前調査が必須
文章多めの解説で読みにくい内容となり申し訳ございません。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。



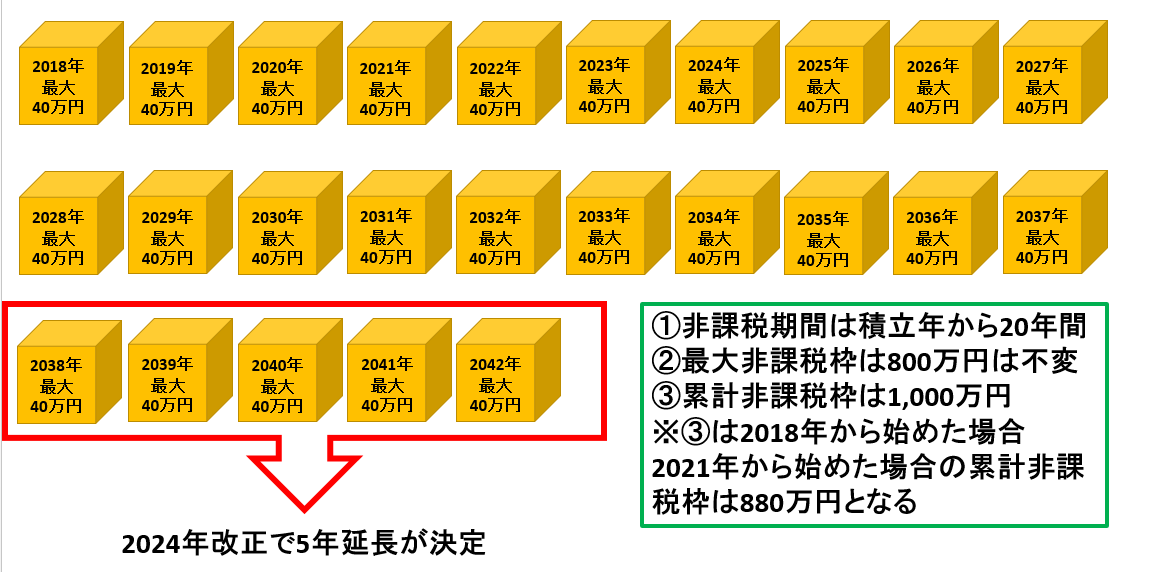





コメント